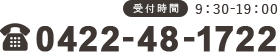2016.01.24
●かいぼら~ず●

井の頭池のかいぼりの様子のつづきです。
環境イベントとしては、結構大規模な感じで、環境省のブースと東京都環境局のブースが出ていました。
先日の外来種の会議のときの担当官が偶然にも環境省のブースに参加されており、さらに偶然にも、野鳥の救護の仕事で以前おつきあいのあった都職員の方が東京都環境局のブースにて陣頭指揮をとっていらっしゃったので御挨拶にいきました。
土曜にも働く公務員の姿というのはイノカシラフラスコモの自生くらい珍しい姿なんじゃないかと思いましたが、環境関連の役所では、国立公園などの現場配置になると土日の仕事がとても多いそうです。
なお、イノカシラフラスコモというのは、今から60年ほど前に井の頭池周辺で発見された水草の一種です。井の頭フラスコ藻 という意味なんでしょうかね。フラスコってあの実験で使うフラスコ? よくわかりませんが、発見から今日まで、日本の水辺の環境は悪化の一途をたどりましたので、いまでは全国で一か所、千葉県のどこぞの池だけに自生が確認されているのだそうです。
かいぼり作戦では、かつて自生がみられたけれども絶滅してしまった水草の種を水底から回収して、特殊な技術で発芽させ、人の管理下でしばしの間、栽培し、再び池にもどしてかつての生態系を回復する という作業も行われているのだそうです。
子供のころに読んだ、大賀一郎博士の古代蓮の研究の話を思い出しました。古代にこぼれおちた植物の種が、タイムカプセルのように現代で息をふきかえし、青々と茂る様は感動ものです。
そんなわけで、繊細な植物をワシワシ食べてしまう、外来の破壊的な生き物を根絶せねばならず、とにかく大正時代の池にはいなかったであろうと考えられる生き物は全て捕獲されていくようです。外来というと外国の生き物というイメージが強いですが、特殊な閉鎖的な生態系にとっては、本来そこにいなかった生き物はすべて外来生物として扱うべきで、井の頭池でいえば、ゲンゴロウブナやクサガメですら移入種と見なし、排除の対象となります。
寒い中、皆さん大変な作業だと思いますが、ドブのにおいのしなくなった夏のいのかしら池で、夕涼みしながらビールを飲める日が来るかもしれないのは嬉しい限りです。がんばれ!かいぼり隊。
以上。三鷹・吉祥寺のペットドクター いのかしら公園動物病院の石橋でした。
環境イベントとしては、結構大規模な感じで、環境省のブースと東京都環境局のブースが出ていました。
先日の外来種の会議のときの担当官が偶然にも環境省のブースに参加されており、さらに偶然にも、野鳥の救護の仕事で以前おつきあいのあった都職員の方が東京都環境局のブースにて陣頭指揮をとっていらっしゃったので御挨拶にいきました。
土曜にも働く公務員の姿というのはイノカシラフラスコモの自生くらい珍しい姿なんじゃないかと思いましたが、環境関連の役所では、国立公園などの現場配置になると土日の仕事がとても多いそうです。
なお、イノカシラフラスコモというのは、今から60年ほど前に井の頭池周辺で発見された水草の一種です。井の頭フラスコ藻 という意味なんでしょうかね。フラスコってあの実験で使うフラスコ? よくわかりませんが、発見から今日まで、日本の水辺の環境は悪化の一途をたどりましたので、いまでは全国で一か所、千葉県のどこぞの池だけに自生が確認されているのだそうです。
かいぼり作戦では、かつて自生がみられたけれども絶滅してしまった水草の種を水底から回収して、特殊な技術で発芽させ、人の管理下でしばしの間、栽培し、再び池にもどしてかつての生態系を回復する という作業も行われているのだそうです。
子供のころに読んだ、大賀一郎博士の古代蓮の研究の話を思い出しました。古代にこぼれおちた植物の種が、タイムカプセルのように現代で息をふきかえし、青々と茂る様は感動ものです。
そんなわけで、繊細な植物をワシワシ食べてしまう、外来の破壊的な生き物を根絶せねばならず、とにかく大正時代の池にはいなかったであろうと考えられる生き物は全て捕獲されていくようです。外来というと外国の生き物というイメージが強いですが、特殊な閉鎖的な生態系にとっては、本来そこにいなかった生き物はすべて外来生物として扱うべきで、井の頭池でいえば、ゲンゴロウブナやクサガメですら移入種と見なし、排除の対象となります。
寒い中、皆さん大変な作業だと思いますが、ドブのにおいのしなくなった夏のいのかしら池で、夕涼みしながらビールを飲める日が来るかもしれないのは嬉しい限りです。がんばれ!かいぼり隊。
以上。三鷹・吉祥寺のペットドクター いのかしら公園動物病院の石橋でした。